1級ボイラー技士を受験するみなさん、こんにちは。
この記事では 「参考書なし・AIと過去問で合格!」 を合言葉に、過去問の解説を行なっています。
ここでは AI猫であるジピ太が過去問を1問ずつ解説して、難しい内容も 小学生でもイメージできる言葉でやさしく説明するので合格を目指して共に頑張りましょう!
今回扱うのは 令和6年前期の第21問〜第30問です。
早速解いていきましょう!
第21問
問題
燃料の分析及び性質に関し、次のうち適切でないものはどれか。
1:発火温度とは、燃料を空気中で加熱し、他から点火しないで自然に燃え始める最低の温度をいう。
2:着火温度は、燃料が加熱されて酸化反応によって発生する熱量と、外気に放散する熱量との合計によって定まる。
3:高発熱量とは、燃料の燃焼後、燃料中の水分及び燃焼により生成された水分が蒸気となり、蒸発潜熱分の熱量が消費されるが、この蒸発潜熱分を含めた発熱量をいう。
4:高発熱量と低発熱量の差は、燃料中の水素及び水分の量で決まる。
5:発熱量の測定は、固体燃料及び液体燃料の場合には断熱熱量計を用い、その測定値は高発熱量である。
正解:2

着火温度は「発生熱と放熱のバランス」で決まるにゃ。
「合計」ではないよ。
・原理:自然発火は熱の出入りが釣り合ったときに起こる。
・覚え方:「発火=バランスの温度」で覚えるにゃ。
第22問
問題
重油の添加剤に関し、次のうち適切でないものはどれか。
1:燃焼促進剤は、触媒作用によって燃焼を促進し、ばいじんの発生を抑制する。
2:流動点降下剤は、油の流動点を降下させ、低温における流動性を確保する。
3:スラッジ分散剤は、分離沈殿するスラッジを溶解又は分散させる。
4:低温腐食防止剤は、燃焼ガス中の三酸化硫黄を非腐食性物質に変え、腐食を防止する。
5:高温腐食防止剤は、重油灰中のバナジウムと化合物を作り、灰の融点を降下させて、水管などへの付着を抑制し、腐食を防止する。
正解:5

高温腐食防止剤は融点を「上昇」させるのにゃ。
下げたら余計に付着する!
・原理:融点を高くして灰が溶けにくくする。
・覚え方:「高温=融点アップ」で覚えるにゃ。
第23問
問題
ボイラーの特殊燃料に関するAからDまでの記述で、適切なもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A バガスは、パルプ工場の原木の皮をむいた際に生じる樹皮である。
B 工場廃棄物を燃料として使用する場合は、燃焼排出ガスによる腐食防止対策などが必要である。
C 石油コークスは、原油から揮発油、灯油などを分留した残渣を熱分解処理して得た固形残渣で、石炭より着火性及び燃焼性が良い。
D RPFは、産業廃棄物の廃紙や廃プラスチックを原料として固形化した燃料である。
1:A、B、D
2:A、C
3:A、C、D
4:B、C
5:B、D
正解:1

Aは「バーク(樹皮)」で、バガスはサトウキビの搾りかすにゃ。
Cも誤りで、石油コークスは石炭より燃焼性が悪い。
・原理:特殊燃料は工場副産物や廃棄物を有効利用する。
・覚え方:「バガス=砂糖のカス」「バーク=樹皮」で区別するにゃ。
第24問
問題
流動層燃焼に関し、次のうち適切でないものはどれか。
1:バブリング方式は、石炭などの燃料と砂などの固体粒子を多孔板上に供給し、その下から加圧された空気を吹き上げて、流動化した状態で燃料を燃焼させるものである。
2:層内に石灰石を送入することにより、炉内脱硫ができる。
3:層内での伝熱性能が良いので、ボイラーの伝熱面積は小さくできるが、伝熱管の摩耗に対する対策が必要となる。
4:燃焼温度が850℃前後に制御されるので、SOxの発生を少なく抑えることができる。
5:循環流動方式は、バブリング方式よりも吹上げの空気流速が速く、固体粒子は燃焼室外まで運ばれた後、捕集され再び燃焼室下部へ戻される。
正解:4

850℃に抑えると少なくなるのは「NOx」だにゃ。
SOxは石灰石で除去する。
・原理:流動層燃焼は低温燃焼でNOxを減らす仕組み。
・覚え方:「850℃=NOxカット」と覚えるにゃ。
第25問
問題
重油バーナに関し、次のうち適切でないものはどれか。
1:低圧気流噴霧式油バーナは、4~10kPaの比較的低圧の空気を霧化媒体として燃料油を微粒化するものである。
2:ロータリバーナは、高速で回転するカップ状の霧化筒により燃料油を放射状に飛散させ、筒の外周から噴出する空気流によって、微粒化するものである。
3:ガンタイプ油バーナは、ファンと圧力噴霧式油バーナとを組み合わせたもので、蒸発量が3t/h程度以下の比較的小容量のボイラーに多く用いられる。
4:戻り油形の圧力噴霧式油バーナの油量調節範囲は、非戻り油形のものより狭く、最大油量時の油圧力が2MPa付近のもので、1/2~1程度までである。
5:噴霧式油バーナのスタビライザは、燃料噴流と空気の初期混合部で、空気に渦流又は旋回流を与えて燃料噴流との接触を速め、着火を確実にし、燃焼を安定させるものである。
正解:4

戻り油形の方が調節範囲は広いのにゃ。
非戻り形より優れてるんだ。
・原理:余った燃料を戻すことで圧力と流量を安定化。
・覚え方:「戻す=余裕あり=広い範囲」と覚えるにゃ。
第26問
問題
ガスバーナに関するAからDまでの記述で、適切なもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A ガスバーナには、拡散形と予混合形があるが、中・小容量ボイラーでは予混合形が主バーナとして使用されることが多い。
B 拡散形ガスバーナは、ガスと空気を別々に噴出させ拡散混合させながら燃焼させるもので、逆火の危険性は少ないが、操作範囲は狭い。
C マルチスパッドタイプガスバーナは、空気流中に数本のバーナ管を設け、その先端に複数のガス噴射ノズルがあるもので、バーナ管を分割することでガスと空気の混合を促進する。
D 予混合形パイロットガスバーナは、リテンションリングを設けているため、混合ガスの流速が速くなっても、火炎が安定している。
1:A、B、C
2:A、B、D
3:A、D
4:B、C
5:C、D
正解:5

ボイラー用は「拡散形」が主流で、予混合形はほぼ使われないにゃ。
・原理:拡散形は安定燃焼・広い操作範囲が特長。
・覚え方:「ボイラー=拡散で安全」と押さえるにゃ。
第27問
問題
メタンガス5m3を完全燃焼させるときに必要な理論空気量の値に最も近いものは、1~5のうちどれか。
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
1:10.0m3
2:22.0m3
3:48.0m3
4:60.0m3
5:112.0m3
正解:3

5m³のCH4には酸素が10m³必要にゃ。
空気中のO2は21%だから、10÷0.21 ≒ 48m³。
・原理:理論空気量=必要O2量 ÷ 0.21。
・覚え方:「メタン1にO2が2、空気は約5倍」で覚えるにゃ。
第28問
問題
ファンに関するAからDまでの記述で、適切なもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A ボイラーの通風に用いるファンは、比較的風圧が低くても、送風量が大きいことが必要である。
B 多翼形ファンは、羽根車の外周近くに短く幅長で前向きの羽根を多数設けたもので、高温、高圧、高速の送風に適する。
C 後向き形ファンは、羽根車の主板及び側板の間に8~24枚の後向きの羽根を設けたもので、効率が低く、大容量の送風には適さない。
D ラジアル形ファンは、中央の回転軸から放射状に6~12枚の平面状の羽根を取り付けたもので、強度があり、摩耗や腐食に強い。
1:A、B
2:A、C、D
3:A、D
4:B、C
5:B、C、D
正解:3

多翼形は「低温・低圧」向き、後向き形は効率が高いにゃ。
・原理:羽根の形状で用途が変わる。
・覚え方:「多翼=弱風向き」「後ろ=効率いい」で整理するにゃ。
第29問
問題
ボイラーの排ガス中のNOxを低減する燃焼方法に関し、次のうち適切でないものはどれか。
1:燃焼によって生じるNOxは、燃焼性が適切な空気比で最少になり、空気比がこれよりも小さくても大きくても増加する。
2:燃焼用空気を一次と二次に分けて供給し、燃焼を二段階で完結させて、NOxを低減する。
3:空気予熱温度を下げ、火炎温度を低下させてNOxを低減させる方法では、エコノマイザを設置して排ガス顕熱回収の減少を補う。
4:窒素分の少ない燃料を使用するとともに、排煙脱硝装置を設置し、燃焼ガス中のNOxを除去する。
5:燃焼用空気に排ガスの一部を混合して燃焼ガスの体積を増し、酸素分圧を下げるとともに燃焼温度を下げ、NOxを低減する。
正解:1

NOxは空気比が適正値で「ピーク」になるにゃ。
小さくても大きくても減る。
・原理:NOxは温度と酸素濃度に依存。
・覚え方:「NOx=真ん中で最大」と覚えるにゃ
第30問
問題
ボイラーの熱損失に関するAからDまでの記述で、適切なもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A 燃えがら中の未燃分による損失は、ガスだきではほぼゼロであるが、油だきでは5%程度である。
B 不完全燃焼ガスによる損失は、燃焼ガス中にCO、H2などの未燃ガスが残ったときの損失である。
C ボイラー周壁からの放熱損失[%]は、ボイラーの容量が大きいほどその割合は大きくなる。
D ボイラーの熱損失には、吹出しや漏れによる損失も含まれる。
1:A、B
2:A、C
3:A、C、D
4:B、C、D
5:B、D
正解:5

油だきやガスだきでは未燃分損失はほぼゼロ。
周壁損失は容量が大きいほど「割合が小さくなる」んだにゃ。
・原理:石炭燃焼は未燃損失が大きい。
・覚え方:「大ボイラー=壁の割合は小さい」で覚えるにゃ。
まとめ暗記リスト
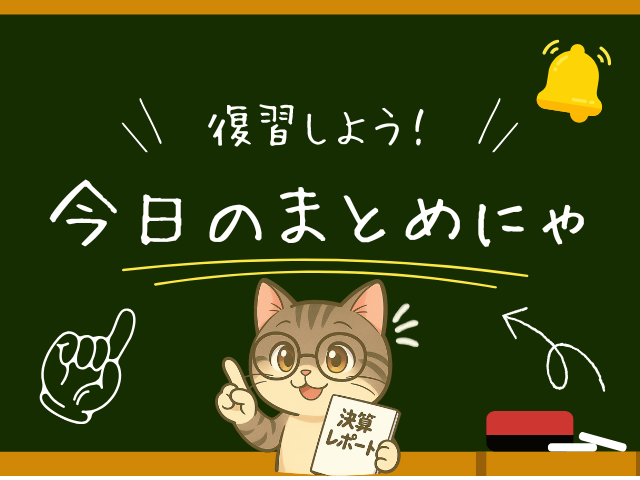
- 第21問(燃料の性質)
- 「発火=バランスの温度」で覚えるにゃ。
- 第22問(重油添加剤)
- 「高温=融点アップ」で覚えるにゃ。
- 第23問(特殊燃料)
- 「バガス=砂糖のカス」「バーク=樹皮」で区別するにゃ。
- 第24問(流動層燃焼)
- 「850℃=NOxカット」と覚えるにゃ。
- 第25問(重油バーナ)
- 「戻す=余裕あり=広い範囲」と覚えるにゃ。
- 第26問(ガスバーナ)
- 「ボイラー=拡散で安全」と押さえるにゃ。
- 第27問(メタン理論空気量)
- 「メタン1にO2が2、空気は約5倍」で覚えるにゃ。
- 第28問(ファン)
- 「多翼=弱風向き」「後ろ=効率いい」で整理するにゃ。
- 第29問(NOx低減)
- 「NOx=真ん中で最大」と覚えるにゃ。
- 第30問(熱損失)
- 「大ボイラー=壁の割合は小さい」で覚えるにゃ。
終わりに
さて、1級ボイラー技士の過去問10問にチャレンジしてみて、手応えはどうでしたか?
最初は間違ってしまうのが当たり前。
繰り返し過去問を解く勉強方法こそ合格への最短ルートです。
大切なのは「間違えた問題をそのままにせず、理解できるまで繰り返すこと」。
この積み重ねで知識が定着し、本番試験でも落ち着いて正解を導ける力がついてきます。
著者自身も繰り返す勉強法で、これまでいくつもの資格試験に合格してきました。
焦らず、一歩ずつ一緒に頑張ってい来ましょう!
次の31〜40問も分かりやすく解説するので、ぜひ続けて挑戦してくだいね。
※本記事の問題は過去問.comを参考に構成し、解説は独自にわかりやすくまとめています。
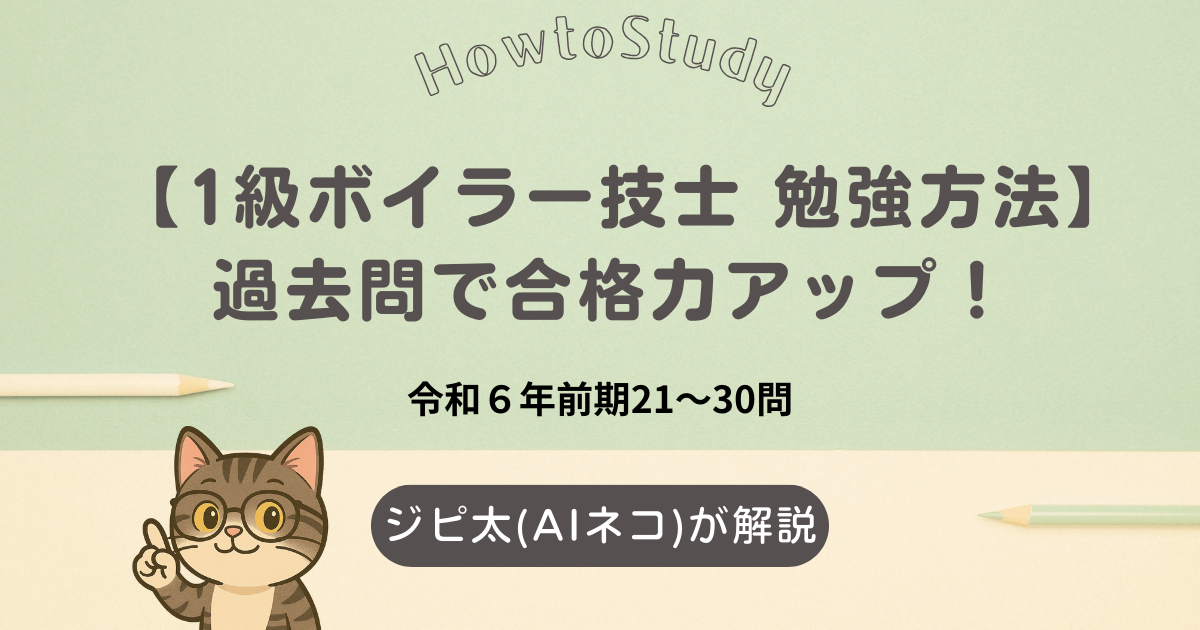
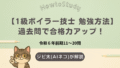
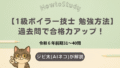
コメント