1級ボイラー技士を受験するみなさん、こんにちは。
この記事では 「参考書なし・AIと過去問で合格!」 を合言葉に、過去問の解説を行なっています。
ここでは AI猫であるジピ太が過去問を1問ずつ解説して、難しい内容も 小学生でもイメージできる言葉でやさしく説明するので合格を目指して共に頑張りましょう!
今回扱うのは 令和6年前期の第1問〜第10問です。
早速解いていきましょう!
第1問
問題
伝熱に関し、次のうち適切でないものはどれか。
1:固体壁の表面とそれに接する流体との間の熱移動を熱伝達といい、液体の沸騰又は蒸気の凝縮のように相変化を伴う場合の熱伝達率は極めて高い。
2:熱伝達によって伝わる熱量は、流体と固体壁表面との温度差及び伝熱する面積に比例する。
3:放射伝熱は、物体が保有する内部エネルギーの一部を電磁波の形で放出し、それが空間を隔てた他の物体面に当たり吸収される熱移動である。
4:放射伝熱によって伝わる熱量は、高温物体の絶対温度と低温物体の絶対温度との差の四乗に比例する。
5:固体壁を通して高温流体から低温流体への熱移動を熱通過又は熱貫流といい、一般に熱伝達及び熱伝導が総合されたものである。
正解:4

放射熱量は「高温側T₁の4乗−低温側T₂の4乗」に比例で、「(T₁−T₂)の4乗」ではないにゃ。
・原理:シュテファン=ボルツマン則(放射は温度の4乗スケール)にゃ。
・覚え方:「高温⁴−低温⁴」でワンセットにゃ。
第2問
問題
次の状況で運転しているボイラーのボイラー効率の値に最も近いものは、1~5のうちどれか。
蒸発量—–2t/h
発生蒸気の比エンタルピ—–2780kJ/kg
給水温度—–23℃
燃料の低発熱量—–39.6MJ/kg
燃料消費量—–154kg/h
1:86%
2:88%
3:90%
4:92%
5:94%
正解:2

「出た熱(2,000×(2780−23×4.187))」÷「入れた熱(154×39,600)」×100 ≒ 88% になるにゃ。
・原理:効率=熱出力÷燃料入熱×100(エンタルピ差で計算)にゃ。
・覚え方:「出た熱÷入れた熱×100」だけ覚えれば計算は迷わないにゃ。
第3問
問題
炉筒煙管ボイラーに関し、次のうち適切でないものはどれか。
1:伝熱面積は20~150m2、蒸発量は10t/h程度までのものが多いが、蒸発量30t/h程度のものもある。
2:「戻り燃焼方式」の燃焼ガスは、炉筒前部から炉筒後部へ流れ、そして炉筒後部で反転して前方に戻る。
3:ドライバック式は、後部煙室が胴の後部鏡板の内に設けられた構造である。
4:エコノマイザや空気予熱器を設け、ボイラー効率が90%以上のものがある。
5:煙管には、平滑管よりも熱伝達率を上げたスパイラル管を用いているものが多い。
正解:3

ドライバックの後部煙室は胴の外にあるにゃ。
内側はウェットバックだにゃ。
・原理:ドライ=耐火材で遮へい、ウェット=水で冷却(後部鏡板が水側)にゃ。
・覚え方:「ドライ=外、ウェット=内」で区別するにゃ。
第4問
問題
水管ボイラーに関し、次のうち適切でないものはどれか。
1:燃焼室を自由な大きさに作ることができるので燃焼状態が良く、種々の燃料及び燃焼方式に対して適応性がある。
2:一般に水冷壁構造であり、水冷壁管は、火炎からの強い放射熱を有効に吸収し、高い蒸発率を示す放射伝熱面になる。
3:自然循環式の大容量のボイラーには、対流形過熱器とともに火炉上方に放射熱を吸収する放射形過熱器を設けたものがある。
4:高温高圧のボイラーでは、本体伝熱面が水冷壁管だけからなり、接触伝熱面しかない放射ボイラーの形式となる。
5:給水及びボイラー水の処理に注意を要し、特に高圧のボイラーでは厳密な水管理を行う必要がある。
正解:4

「接触伝熱面しかない」は逆にゃ。
高温高圧は『放射主体(ほぼ水冷壁)』で、対流面は少ないorなしにゃ。
・原理:火炉で放射吸収→上流に放射形過熱器、下流に対流形過熱器を配置するのが定番にゃ。
・覚え方:「高温高圧=放射でドーン!」にゃ。
第5問
問題
ボイラー各部の構造及び強さに関し、次のうち適切でないものはどれか。
1:胴板を一般に薄肉円筒として取り扱う場合、長手方向の断面に生じる周方向の応力は、周方向の断面に生じる長手方向の応力の2倍となる。
2:皿形鏡板は、球面殻、環状殻及び円筒殻から成っており、環状殻の部分には内圧により曲げ応力が生じる。
3:皿形鏡板は、同材質、同径、同厚の場合、全半球形鏡板より強度が低い。
4:炉筒の鏡板への取付けは、鏡板の炉筒取付け部分を内方に折り込んで、すみ肉溶接によって行うのが一般的である。
5:波形炉筒は、平形炉筒に比べ、熱による炉筒の伸縮を吸収でき、外圧に対する強度も高い。
正解:4

炉筒の取付けは内方に折り込んで突合せ溶接が一般的。
すみ肉溶接ではないにゃ。
・原理:受圧部の主要継手は完全溶け込みの突合せで応力集中を低減にゃ。
・覚え方:「炉筒はツキ(突)合せで強度キープ」にゃ。
第6問
問題
空気予熱器に関し、次のうち適切でないものはどれか。
1:鋼板形の熱交換式空気予熱器は、鋼板を一定間隔に並べて端部を溶接し、1枚おきに空気及び燃焼ガスの通路を形成したものである。
2:再生式空気予熱器は、熱交換式空気予熱器に比べ、空気側とガス側との間に漏れが多いが、伝熱効率が良いためコンパクトな形状にすることができる。
3:ヒートパイプ式空気予熱器は、金属製の管の中にアンモニア、水などの熱媒体を減圧して封入し、高温側で熱媒体を蒸発させ、低温側で熱媒体蒸気を凝縮させて、熱を移動させるものである。
4:空気予熱器を設置することにより燃焼効率が上がり、過剰空気量が少なくてすむ。
5:空気予熱器の設置による通風抵抗の増加は、エコノマイザの設置による通風抵抗の増加より小さい。
正解:5

通風抵抗は一般に空気予熱器の方が大きいにゃ。
エコノマイザより小さい、は逆だにゃ。
・原理:フィンや仕切り等で流路が複雑→圧力損失増にゃ。
・覚え方:「クウヨ(空予)は抵抗“強”」で覚えるにゃ。
第7問
問題
ボイラーの附属品及び附属装置に関し、AからDまでの記述のうち、適切なもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A 主蒸気弁に用いる仕切弁は、蒸気入口と出口が直角になったもので、高圧用であるが全開時の抵抗が大きい。
B 減圧弁は、発生蒸気の圧力と使用箇所での蒸気圧力の差が大きいとき、又は使用箇所での蒸気圧力を一定に保つときに設けられる。
C 沸水防止管は、大径のパイプに設けた穴から、蒸気を胴又はドラム内の広い範囲に分散させる装置である。
D 主蒸気管の配置に当たっては、曲がり部に十分な半径をもたせ、ドレンのたまる部分がないように傾斜をつけるとともに、要所に蒸気トラップを設ける。
1:A、B、C
2:A、B、D
3:A、C
4:B、D
5:C、D
正解:4

仕切弁=「まっすぐスッと通って抵抗小」
減圧弁=「高い蒸気はちょっと下げて使いやすく」
沸水防止管=「蒸気の向きを変えて水滴バイバイ」
主蒸気管=「曲がりはゆるやか、ドレンは逃がす」
第8問
問題
ボイラーに使用する計測器に関し、次のうち適切でないものはどれか。
1:差圧式流量計は、流体が流れている管の中にベンチュリ管又はオリフィスなどの絞り機構を挿入すると、流量がその入口と出口の差圧の二乗に比例することを利用している。
2:面積式流量計は、テーパ管の中を流体が下から上に流れると、フロートが流量に応じて上下し、流量がテーパ管とフロートの間の環状面積に比例することを利用している。
3:平形反射式水面計は、光の通過と反射の作用によって、蒸気部は白く水部は黒く見えるようにしたもので、最高使用圧力2.5MPa以下のボイラーに使用できる。
4:平形透視式水面計は、裏側から電灯の光を通して水面を見分けるもので、型式により、最高使用圧力12MPa以下のボイラーに使用できる。
5:マルチポート形水面計は、金属製の箱に小さい丸い窓を縦に配列し、円形透視式ガラスをはめ込んだもので、最高使用圧力21MPa以下のボイラーに使用できる。
正解:1

差圧式流量計の流量は差圧の平方根に比例にゃ。
「二乗」は逆だにゃ。
・原理:ベルヌーイ+連続の式→ Q∝ΔPQ \propto \sqrt{\Delta P} にゃ。
・覚え方:「差圧は“√”で読む」と覚えるにゃ。
第9問
問題
ボイラーにおける燃焼安全装置の火炎検出器に関するAからDまでの記述で、適切なもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A フォトダイオードセルは、光起電力効果を利用したもので、形状・寸法が小形であり、ガンタイプ油バーナなどに多く用いられる。
B 硫化鉛セルは、炉壁の放射による誤作動がなく、ガス専焼バーナに用いられるが、蒸気噴霧式油バーナには適さない。
C 整流式光電管は、光電子放出現象を利用したもので、油燃焼炎の検出に用いられるが、ガス燃焼炎には適さない。
D フレームロッドは、火炎の導電作用を利用したもので、ロッドの使用温度による制約があることから、主に油燃焼炎の検出に用いられる。
1:A、B、C
2:A、C
3:A、D
4:B、C、D
5:B、D
正解:2

A○(小形で油バーナに多用)、B×(硫化鉛セルは油炎のフリッカ検出で用いられる)、C○(整流式光電管は油炎向け/ガスは不適)、D×(フレームロッドは主にガス炎検出)にゃ。
・原理:検出器は炎の特性(発光波長・フリッカ・導電性)に合わせて使い分けるにゃ。
・覚え方:「油=フォト/光電、ガス=フレームロッド」にゃ。
第10問
問題
ボイラーの自動制御に関し、次のうち適切でないものはどれか。
1:シーケンス制御は、あらかじめ定められた順序に従って、制御の各段階を、順次、進めていく制御である。
2:フィードフォワード制御は、出力側の信号を入力側に戻すことによって、制御量の値を目標値と比較し、それらを一致させるように訂正動作を行う制御である。
3:オンオフ動作は、操作量が二つの値のいずれかをとる2位置動作のうち、その位置の一つをゼロとするものである。
4:積分動作は、単独で用いられることはなく、比例動作と組み合わせてPI動作という形で用いられる。
5:微分動作は、制御偏差が変化する速度に比例して操作量を増減させるように働く動作で、D動作ともいう。
正解:2

記述はフィードバックの説明にゃ。
フィードフォワードは外乱を先読みして補正する方式だにゃ。
・原理:FB=出力を戻して誤差修正/FF=外乱モデルで先回り補正にゃ。
・覚え方:「バック=戻す」「フォワード=先回り」と覚えるにゃ。
まとめ暗記リスト
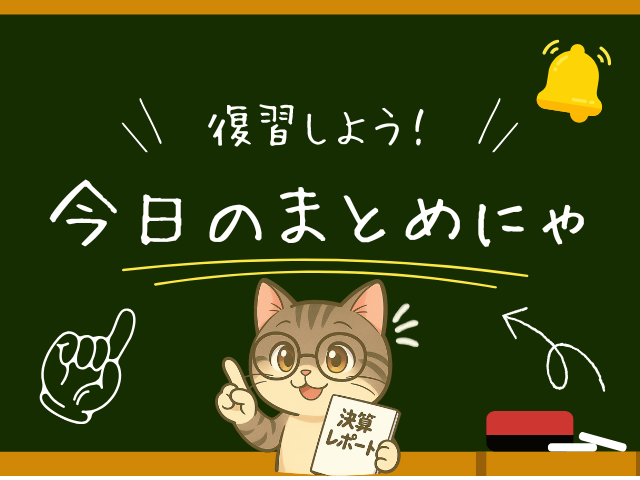
- 第1問(伝熱)
- 「放射熱=高温⁴ − 低温⁴」だにゃ。
- 第2問(効率計算)
- 「出た熱 ÷ 入れた熱 ×100」だにゃ。
- 第3問(炉筒煙管ボイラー)
- 「ドライ=外、ウェット=内」だにゃ。
- 第4問(水管ボイラー)
- 「高温高圧=放射でドーン!」だにゃ。
- 第5問(構造と強さ)
- 「炉筒は突合せで強く!」だにゃ。
- 第6問(空気予熱器)
- 「空予の抵抗>エコノ」だにゃ。
- 第7問(附属装置)
- 仕切弁=「まっすぐスッと通って抵抗小」
- 減圧弁=「高い蒸気はちょっと下げて使いやすく」
- 沸水防止管=「蒸気の向きを変えて水滴バイバイ」
- 主蒸気管=「曲がりはゆるやか、ドレンは逃がす」
- 第8問(計測器)
- 「差圧式は√に比例」だにゃ。
- 第9問(火炎検出器)
- 「油=光、ガス=ロッド」だにゃ。
- 第10問(自動制御)
- 「バック=戻す、フォワード=先回り」だにゃ。
終わりに
さて、1級ボイラー技士の過去問10問にチャレンジしてみて、手応えはどうでしたか?
最初は間違ってしまうのが当たり前。
繰り返し過去問を解く勉強方法こそ合格への最短ルートです。
大切なのは「間違えた問題をそのままにせず、理解できるまで繰り返すこと」。
この積み重ねで知識が定着し、本番試験でも落ち着いて正解を導ける力がついてきます。
著者自身も繰り返す勉強法で、これまでいくつもの資格試験に合格してきました。
焦らず、一歩ずつ一緒に頑張ってい来ましょう!
次の11〜20問も分かりやすく解説するので、ぜひ続けて挑戦してくだいね。
※本記事の問題は過去問.comを参考に構成し、解説は独自にわかりやすくまとめています。
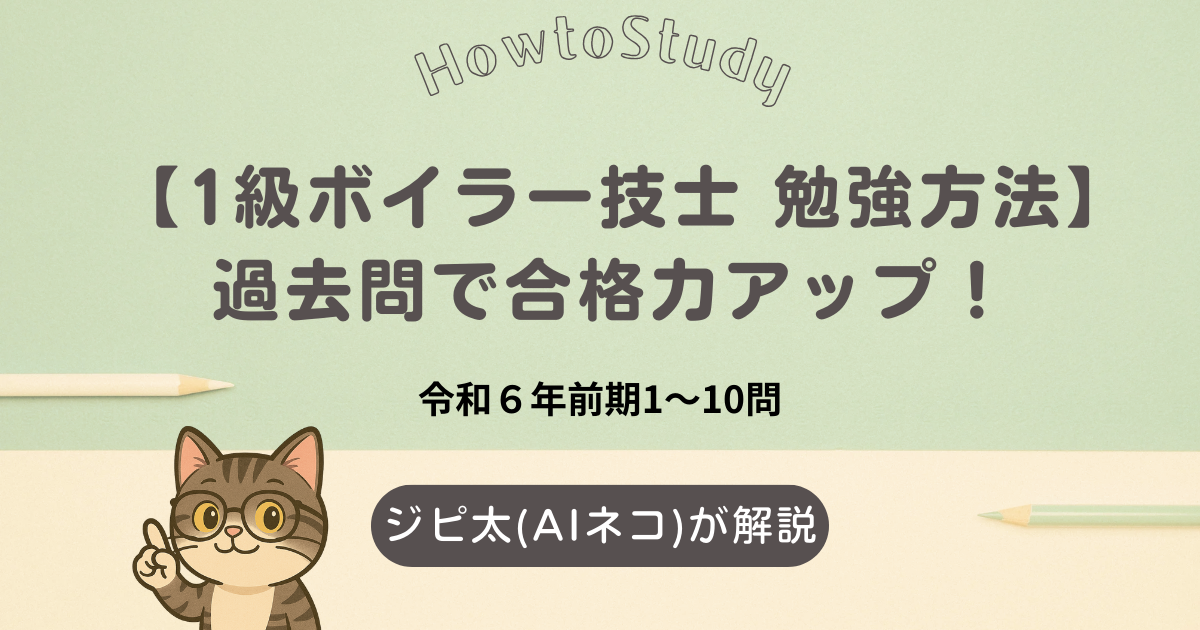
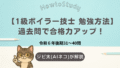
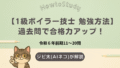
コメント