1級ボイラー技士を受験するみなさん、こんにちは。
この記事では 「参考書なし・AIと過去問で合格!」 を合言葉に、過去問の解説を行なっています。
ここでは AI猫であるジピ太が過去問を1問ずつ解説して、難しい内容も 小学生でもイメージできる言葉でやさしく説明するので合格を目指して共に頑張りましょう!
今回扱うのは 令和6年前期の第31問〜第40問です。
早速解いていきましょう!
第31問
問題
法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
1:伝熱面積が14m2の温水ボイラー
2:伝熱面積が4m2の蒸気ボイラーで、胴の内径が800㎜、かつ、その長さが1500㎜のもの
3:伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー
4:内径が400mmで、かつ、その内容積が0.2m3の気水分離器を有する伝熱面積が25m2の貫流ボイラー
5:伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー
正解:2

3m2を超える蒸気ボイラーは「小規模ボイラー」扱いではなく、ボイラー技士が必要になるにゃ。
・原理:小規模ボイラーは一定の条件を満たせば講習修了者でも扱える。
・覚え方:「蒸気ボイラーは3m2を超えたら技士にゃ!」で覚えるとスッキリだにゃ。
第32問
問題
ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の設置、検査及び検査証に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
A ボイラーを輸入した者は、原則として、使用検査を受けなければならない。
B 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
C ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、原則として登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
D 設置されたボイラーに関し事業者に変更があったときは、変更後の事業者は、その変更後14日以内に、所轄労働基準監督署長にボイラー検査証書替申請書を提出しなければならない。
1:A、B、C
2:A、C
3:A、D
4:B、C、D
5:B、D
正解:2

再設置は「使用再開検査」ではなく再度「使用検査」になるにゃ。
申請期限も14日ではなく10日。
・原理:検査証や申請は安全のために期限が厳密に決まっている。
・覚え方:「輸入と更新はOK、再設置と事業者変更は要注意!」で覚えるにゃ。
第33問
問題
ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の設置場所等に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
1:伝熱面積が3m2をこえるボイラーは、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない。
2:ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がない場合を除き、1.2m以上としなければならない。
3:胴の内径が500㎜以下で、かつ、長さが1000㎜ 以下の立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を0.3m以上としなければならない。
4:ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物については、金属材料で被覆しなければならない。
5:ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には、2以上の出入口を設けなければならない。
正解:4

金属ではなく「不燃性材料」で被覆する決まりだにゃ。
・原理:熱で燃えない素材で火災を防ぐ。
・覚え方:「煙突近くは“金属”じゃなく“不燃材”」で覚えるにゃ。
第34問
問題
ボイラー取扱作業主任者の職務に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A 1日に1回以上安全弁の機能を点検すること。
B 適宜、吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
C 給水装置の機能の保持に努めること。
D 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
1:A、B
2:A、B、C
3:A、D
4:B、C、D
5:C、D
正解:4

1日1回点検が必要なのは「水面測定装置」で、安全弁ではないにゃ。
・原理:主任者の職務は「水管理・記録・装置管理」。
・覚え方:「吹出し・給水・ばい煙記録!」の3点セットにゃ。
第35問
問題
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
1:燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護しなければならない。
2:水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が100℃以上の温度にならない措置を講じなければならない。
3:蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示しなければならない。
4:圧力計の目もりには、ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をしなければならない。
5:逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講じなければならない。
正解:2

基準は「80℃以上」だにゃ。
100℃ではない。
・原理:水高計は凍結や高温から守る必要がある。
・覚え方:「水高計=80℃が基準」と覚えるにゃ。
第36問
問題
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A 定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「燃焼装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければならない。
B ボイラーについて、その使用を開始した後、2月以内ごとに1回、定期自主検査を行わなければならない。
C 定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを2年間保存しなければならない。
D 定期自主検査を行った場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
1:A、B、C
2:A、B、D
3:A、D
4:B、C
5:C、D
正解:3

間隔は「1か月ごと」、保存は「3年間」だにゃ。
・原理:自主検査は定期性と記録保存が必須。
・覚え方:「1か月・3年・異常は修理」のセットで覚えるにゃ。
第37問
問題
鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)に取り付ける温度計、圧力計及び水高計に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
1:温水ボイラーの水高計の目盛盤の最大指度は、常用使用圧力の1.5倍以上3倍以下の圧力を示す指度としなければならない。
2:温水ボイラーの水高計は、コック又は弁の開閉状況を容易に知ることができるようにしなければならない。
3:温水ボイラーには、ボイラーの出口付近における温水の温度を表示する温度計を取り付けなければならない。
4:蒸気ボイラーには、過熱器の出口付近における蒸気の温度を表示する温度計を取り付けなければならない。
5:蒸気ボイラーの圧力計は、蒸気が直接入らないようにしなければならない。
正解:1

「常用使用圧力」ではなく「最高使用圧力」が基準にゃ。
・原理:圧力計の表示範囲は安全確保のため最高使用圧力を基準に設定。
・覚え方:「圧力計は“最高”で決める」と覚えるにゃ。
第38問
問題
鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の安全弁及び逃がし弁に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
1:貫流ボイラー以外の蒸気ボイラーの安全弁は、ボイラー本体の容易に検査できる位置に直接取り付け、かつ、弁軸を鉛直にしなければならない。
2:貫流ボイラーに備える安全弁については、当該ボイラーの最大蒸発量以上の吹出し量のものを過熱器の出口付近に取り付けることができる。
3:過熱器には、過熱器の出口付近に過熱器の温度を設計温度以下に保持することができる安全弁を備えなければならない。
4:蒸気ボイラーには、安全弁を2個以上備えなければならないが、伝熱面積が50m2以下の蒸気ボイラーにあっては、安全弁を1個とすることができる。
5:水の温度が120℃以下の温水ボイラーには、容易に検査ができる位置に、内部の圧力を最高使用圧力以下に保持することができる逃がし管を備えたものを除き、安全弁を備えなければならない。
正解:3

必要なのは「逃がし弁」であって安全弁ではないにゃ。
・原理:温水ボイラーは蒸気を作らないので逃がし弁で安全管理。
・覚え方:「温水=逃がし弁、蒸気=安全弁」と区別するにゃ。
第39問
問題
鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の給水装置に関し、AからDまでの記述のうち、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A 燃料の供給を遮断してもなおボイラーへの熱供給が続く蒸気ボイラーには、原則として、随時単独に最大蒸発量以上を給水することができる給水装置を3個備えなければならない。
B 近接した2以上の蒸気ボイラーを結合して使用する場合には、結合して使用する蒸気ボイラーを1の蒸気ボイラーとみなして、要件を満たす給水装置を備えなければならない。
C 最高使用圧力1MPa未満の蒸気ボイラーの給水装置の給水管には、給水弁のみを取り付け、逆止め弁は取り付けないことができる。
D 給水内管は、取外しができる構造のものでなければならない。
1:A、B
2:A、B、C
3:A、C、D
4:B、D
5:C、D
正解:4

給水装置は「2個」でよく、圧力条件も0.1MPa未満だにゃ。
・原理:給水の安全性を確保するために最低限の装置数と構造が定められている。
・覚え方:「給水は2個、0.1未満、取り外し可」って覚えると整理できるにゃ。
第40問
問題
鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)に関する次の文中の[ ]内に入れるAからCまでの語句又は数字の組合せとして、該当する法令の内容と一致するものは1~5のうちどれか。
「最高使用圧力[ A ]MPa以上の蒸気ボイラー(移動式ボイラーを除く。)の吹出し管には、吹出し弁を2個以上又は吹出し弁と吹出しコックをそれぞれ[ B ]個以上[ C ]に取り付けなければならない。」
1:A=1 B=1 C=並列
2:A=1 B=1 C=直列
3:A=1 B=2 C=並列
4:A=2 B=2 C=並列
5:A=2 B=2 C=直列
正解:2

基準は「1MPa以上」で、吹出し弁とコックを直列に取り付ける決まりにゃ。
・原理:高圧になると吹出し設備の二重化で安全確保。
・覚え方:「1MPaで直列2重チェック」と覚えるにゃ。
まとめ暗記リスト
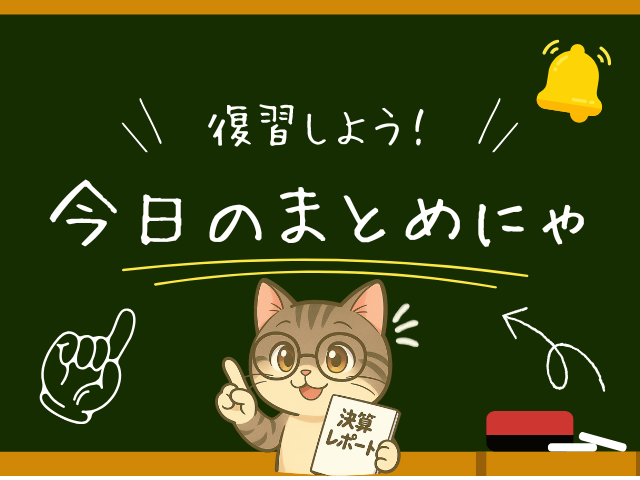
- 第31問(小規模ボイラーの区分)
- 「蒸気ボイラーは3m²を超えたら技士にゃ!」だにゃ。
- 第32問(設置・検査・検査証)
- 「輸入と更新はOK、再設置と事業者変更は要注意!」だにゃ。
- 第33問(設置場所の基準)
- 「煙突近くは“金属”じゃなく“不燃材”」だにゃ。
- 第34問(取扱主任者の職務)
- 「吹出し・給水・ばい煙記録!」の3点セットだにゃ。
- 第35問(附属品の管理)
- 「水高計=80℃が基準」だにゃ。
- 第36問(定期自主検査)
- 「1か月・3年・異常は修理」のセットだにゃ。
- 第37問(計器の規定)
- 「圧力計は“最高”で決める」だにゃ。
- 第38問(安全弁・逃がし弁)
- 「温水=逃がし弁、蒸気=安全弁」だにゃ。
- 第39問(給水装置の規定)
- 「給水は2個、0.1未満、取り外し可」だにゃ。
- 第40問(吹出し弁の取付け)
- 「1MPaで直列2重チェック」だにゃ。
終わりに
さて、1級ボイラー技士の過去問10問にチャレンジしてみて、手応えはどうでしたか?
最初は間違ってしまうのが当たり前。
繰り返し過去問を解く勉強方法こそ合格への最短ルートです。
大切なのは「間違えた問題をそのままにせず、理解できるまで繰り返すこと」。
この積み重ねで知識が定着し、本番試験でも落ち着いて正解を導ける力がついてきます。
著者自身も繰り返す勉強法で、これまでいくつもの資格試験に合格してきました。
焦らず、一歩ずつ一緒に頑張ってい来ましょう!
次の令和5年前期1〜10問も分かりやすく解説するので、ぜひ続けて挑戦してくだいね。
※本記事の問題は過去問.comを参考に構成し、解説は独自にわかりやすくまとめています。
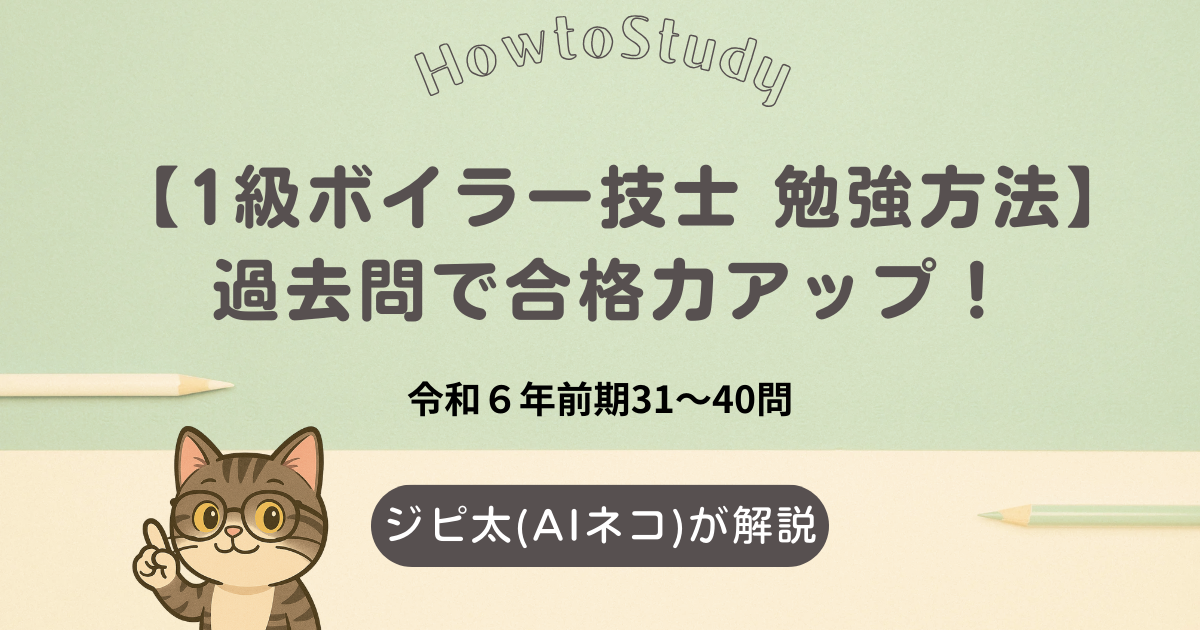
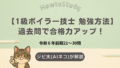
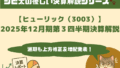
コメント