1級ボイラー技士を受験するみなさん、こんにちは。
この記事では 「参考書なし・AIと過去問で合格!」 を合言葉に、過去問の解説を行なっています。
ここでは AI猫であるジピ太が過去問を1問ずつ解説して、難しい内容も 小学生でもイメージできる言葉でやさしく説明するので合格を目指して共に頑張りましょう!
今回扱うのは 令和6年前期の第11問〜第20問です。
早速解いていきましょう!
第11問
問題
ボイラーの起動時及び蒸気圧力上昇時の取扱いに関するAからDまでの記述で、適切なもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A バーナが横に数個並べられて配置されている場合は、原則として、炉の外側のバーナから点火する。
B 空気予熱器に不同膨張による漏れなどを生じさせないため、燃焼初期はできる限り低燃焼とし、低燃焼中は空気予熱器の出口ガス温度を監視する。
C エコノマイザの前に蒸発管群がない場合は、燃焼ガスを通し始めた後に、ボイラー水の一部をエコノマイザ入口に供給して、エコノマイザ内の水を循環させる。
D ボイラー水の温度が高くなっていくと水位が上昇するので、高水位となったら、ボイラー水を排出して常用水位に戻す。
1:A、B、D
2:A、C
3:A、C、D
4:B、C
5:B、D
正解:5

Aは内側(炉心側)から点火するのが原則だにゃ。
Cは「ガスを通す前」に循環を確保するのが正しいにゃ。
・原理:起動初期は各機器の熱応力を小さくするため低燃焼・温和昇圧が基本だにゃ。
・覚え方:「点火は内→外、予熱は低→様子見」で覚えるにゃ。
第12問
問題
ボイラーの水面計及び圧力計の取扱いに関し、次のうち適切でないものはどれか。
1:運転開始時の水面計の機能試験は、残圧がある場合は点火直前に行い、残圧がない場合には圧力が上がり始めたときに行う。
2:水面計を取り付ける水柱管の水側連絡管の取付けは、ボイラー本体から水柱管に向かって上がり勾配とする。
3:水面計のコックを開くときは、ハンドルが管軸に対し直角方向になるようにする。
4:水柱管の水側連絡管の角曲がり部には、プラグを設けてはならない。
5:圧力計は、原則として、毎年1回、圧力計試験機による試験を行うか、又は試験専用の圧力計を用いて比較試験を行う。
正解:4

角曲がり部にはブローや清掃用にプラグを設けるのが一般的にゃ。
・原理:水面計は詰まりや誤表示が重大事故につながるから、排出・清掃ができる構造が必要だにゃ。
・覚え方:「曲がりに“栓”(プラグ)で安全確保」にゃ。
第13問
問題
ボイラーにおけるキャリオーバに関するAからDまでの記述で、適切なもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A キャリオーバは、ボイラー水に有機物などが存在するときに生じやすい。
B キャリオーバが生じると、過熱器にボイラー水が入り、蒸気温度が過昇する。
C シリカの選択的キャリオーバは、ボイラー水のシリカ濃度が低いほど生じやすい。
D キャリオーバが生じたときは、燃焼量を下げて、圧力計、水面計を見ながら主蒸気弁などを徐々に絞る。
1:A、B
2:A、B、C
3:A、D
4:B、C、D
5:C、D
正解:3

Bは水が入ると過熱器の温度は下がり、汚損や損傷の原因にゃ。
Cは濃度が「高いほど」起こりやすいにゃ。
・原理:泡立ちや微粒子同伴で水が蒸気側へ持ち去られる現象がキャリオーバだにゃ。
・覚え方:「シリカ高→一緒に来る」「トラブル時は燃焼下げて弁しぼる」にゃ。
第14問
問題
ボイラーの送気開始時及び運転中の取扱いに関するAからDまでの記述で、適切なもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A 送気開始時は、ドレンを切り、暖管を十分に行った後、主蒸気弁を段階的に少しずつ開き、全開状態となったら、少し戻しておく。
B 油だきボイラーの火炎に火花が生じる場合は、通風が弱すぎるので、通風計を見ながらドラフトを調節する。
C 運転中、水面計の水位が上下にかすかに動いている場合では、元弁が閉まっているか、又は蒸気側連絡管に詰まりが生じているので、直ちに水面計の機能試験を行う。
D 運転中は、給水ポンプ出口側に取り付けられた圧力計により、吐出量に見合った給水圧力かどうかを監視する。
1:A、B、D
2:A、C
3:A、D
4:B、C
5:B、C、D
正解:3

Bは火花=通風「強すぎ」が原因のことが多いにゃ。
Cは「全く動かない」等で水側詰まりを疑うケースだにゃ。
・原理:燃焼には適正な空気量と炎の保持が必要。
送風が強すぎると火炎が引きちぎられ、火炎保持器から火の粉のように見える現象が起こるにゃ。
・覚え方:「詰まれば不動」「火花=強風」をセットで覚えるにゃ。
正解:3
ジピ太の解説
・なぜ誤りか:Bは火花=通風「強すぎ」が原因のことが多いにゃ。Cは「全く動かない」等で水側詰まりを疑うケースだにゃ。
・原理:送気開始は暖管・ドレン抜き・段階開放が基本、安全側に少し戻すのがコツだにゃ。
・覚え方:「送気は少しずつ→全開ちょい戻し」「火花=強風」をセットで覚えるにゃ。
第15問
問題
ボイラーに給水するディフューザポンプの取扱いに関するAからDまでの記述で、適切なもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A グランドパッキンシール式の軸については、水漏れがないことを確認する。
B 運転前に、ポンプ内及びポンプ前後の配管内の空気を十分に抜く。
C 運転中は、ポンプの吐出し圧力、流量及び負荷電流が適正であることを確認する。
D 運転を停止するときは、ポンプ駆動用電動機を止めた後、吐出し弁を徐々に閉め、全閉にする。
1:A、B、C
2:A、C、D
3:A、D
4:B、C
5:B、D
正解:4

Aは「少量滴下」が正常だにゃ(潤滑・冷却)。
Dは停止手順が逆で、まず吐出し弁を閉めてから停止にゃ。
・原理:ポンプは空気噛み厳禁。
計器で運転点を監視してキャビテーションや過負荷を防ぐにゃ。
・覚え方:「ポンプは“空抜き→計器見張り→弁閉じて停止”」だにゃ。
第16問
問題
ボイラーの自動制御装置の点検に関するAからDまでの記述で、適切なもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A 配管、弁及び導管の接続部並びにシール部から漏出がないか点検する。
B 温度検出器の感温体や保護管は、装置へ完全に挿入して取り付けられているか点検する。
C 比例式圧力調節器は、圧力の設定値や動作すき間の設定値が変わっていないか点検する。
D 燃料遮断弁は、弁外部への燃料漏れ、及び2年に1回程度、内部弁座漏れの有無を点検する。
1:A、B
2:A、B、D
3:A、C、D
4:B、C
5:C、D
正解:1

Cは比例式なら「比例帯」の点検にゃ(オンオフ式は動作すき間)。
Dは内部漏れ点検は通常「年1回」程度にゃ。
・原理:検出器は正しい位置と密着が命、配管・シールの漏れも制御不良の元だにゃ。
・覚え方:「比例は“帯”、オンオフは“すき間”、遮断弁は“毎年”チェック」にゃ。
正解:1
ジピ太の解説
・なぜ誤りか:Cは比例式なら「比例帯」の点検にゃ(オンオフ式は動作すき間)。Dは内部漏れ点検は通常「年1回」程度にゃ。
・原理:検出器は正しい位置と密着が命、配管・シールの漏れも制御不良の元だにゃ。
・覚え方:「比例は“帯”、オンオフは“すき間”、遮断弁は“毎年”チェック」にゃ。
第17問
問題
ボイラー休止中の保存法に関し、次のうち適切でないものはどれか。
1:乾燥保存法では、ボイラー内に蒸気や水が浸入しないように、蒸気管及び給水管のフランジ継手部に閉止板を挟むなどにより、外部と確実に遮断する。
2:乾燥保存法では、活性アルミナ、シリカゲルなどの吸湿剤を容器に入れてボイラー内の数箇所に置き、ボイラーを密閉する。
3:短期満水保存法により10日間程度の期間保存するときは、スラッジなどを排出した後、薬液注入を併用しつつ給水を行い、満水にする。
4:長期満水保存法で1か月以上の期間保存する場合に、窒素でシールする方法を併用すると、再熱器や脱気器に対しても防食上有効である。
5:窒素封入法の窒素の封入条件は、窒素純度98%以上、封入圧力0.1~0.2MPaとするのが一般的である。
正解:5

窒素封入の圧力は一般に0.05〜0.06MPa程度が目安にゃ。
0.1〜0.2MPaは過大だにゃ。
・原理:乾燥(吸湿)か満水(除酸素)で腐食因子を断つ、が保存の基本だにゃ。
・覚え方:「窒素は“ほどほど圧”=0.05〜0.06MPa」にゃ。
第18問
問題
ボイラー水中の不純物に関するAからDまでの記述で、適切なもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A 硫酸塩類やけい酸塩類のスケールは、伝熱面において熱分解して軟質沈殿物になるが、次第に固まり、腐食、過熱などの原因となる。
B スラッジは、溶解性蒸発残留物が濃縮され、ドラム底部などに沈積した軟質沈殿物である。
C 伝熱面にスケールが付着すると、ボイラー水による伝熱面の冷却が不十分となり、伝熱面の温度が上昇する。
D 懸濁物は、溶解性蒸発残留物が濃縮されたもので、水中に浮遊し、キャリオーバの原因となる。
1:A、B、C
2:A、C、D
3:A、D
4:B、C
5:B、D
正解:4

Aのスケール(硫酸塩・けい酸塩)は「熱分解しにくく」硬く固着にゃ。
Dは懸濁物=不溶物・油滴等の浮遊物を指すにゃ。
・原理:スケールは熱抵抗を増やし金属温度を上げる→過熱・焼損リスクだにゃ。
・覚え方:「スケール硬くて熱こもる、スラッジ柔らか溜まりやすい」にゃ。
第19問
問題
蒸発量が280kg/hの炉筒煙管ボイラーに塩化物イオン濃度が15㎎/Lの給水を行い、20kg/hの連続吹出しを行う場合、ボイラー水の塩化物イオン濃度の値は、次のうちどれか。
なお、Lはリットルである。
1:195㎎/L
2:210㎎/L
3:225㎎/L
4:350㎎/L
5:400㎎/L
正解:3

定常(入=出)で物質収支を立てるにゃ。
・原理(1行計算):濃度X=給水濃度×(蒸発量+ブロー量)/ブロー量
=15×(280+20)/20=15×300/20=225 mg/L にゃ。
・覚え方:「入=出、給水濃度(蒸発+ブロー)/ブロー」で一発にゃ。
第20問
問題
ボイラーの腐食、劣化及び損傷に関し、次のうち適切でないものはどれか。
1:異種金属接触腐食は、異種金属がその電位差により水を介して電気的に生じる腐食である。
2:アルカリ腐食は、高温のボイラー水中で濃縮したりん酸カルシウムと鋼材が反応して生じる。
3:膨出は、火炎に触れる水管などが過熱されて強度が低下し、内部の圧力に耐えきれずに外側へ膨れ出る現象である。
4:水側伝熱面の伝熱が妨げられたりすると、伝熱面構成部材の温度が著しく上昇し、過熱、焼損が生じる。
5:ボイラー水位が低下し、水管の取付け部、ステーボルトのねじ込み取付け部などが過熱されることにより漏れが生じる。
正解:2

アルカリ腐食は濃縮した水酸化ナトリウム(NaOH)と鋼の反応が主体にゃ。
りん酸カルシウムではないにゃ。
・原理:付着物下でアルカリ濃縮→応力部で割れや溝状腐食を誘発にゃ。
・覚え方:「アルカリ=ナトリウム」で覚えるにゃ。
まとめ暗記リスト
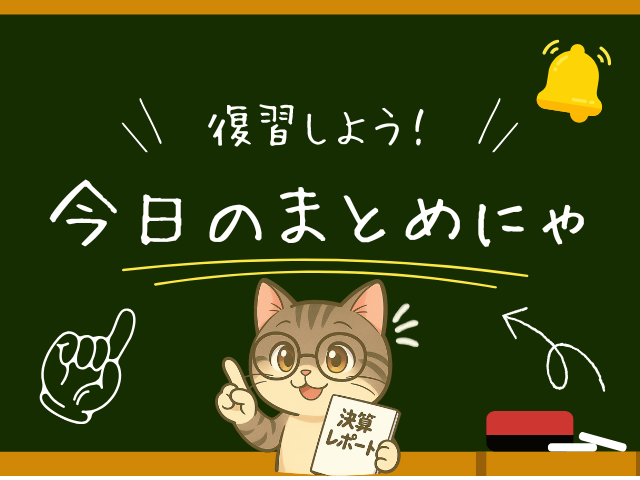
- 第11問(起動・昇圧時)
- 「点火は内→外、予熱は低→様子見」
- 第12問(水面計・圧力計)
- 「曲がりにプラグで安全確保」
- 第13問(キャリオーバ)
- 「シリカ高→一緒に来る」「トラブル時は燃焼下げて弁しぼる」
- 第14問(送気・運転中)
- 「詰まれば不動」「火花=強風」
- 第15問(給水ポンプ)
- 「ポンプは空抜き→計器見張り→弁閉じて停止」
- 第16問(自動制御点検)
- 「比例=帯、オンオフ=すき間、遮断弁は毎年チェック」
- 第17問(保存法)
- 「窒素はほどほど圧=0.05〜0.06MPa」
- 第18問(水中不純物)
- 「スケール硬くて熱こもる、スラッジ柔らか溜まりやすい」
- 第19問(塩化物濃度計算)
- 「入=出、給水濃度(蒸発+ブロー)/ブロー」
- 第20問(腐食・劣化)
- 「アルカリ=ナトリウム」
終わりに
さて、1級ボイラー技士の過去問10問にチャレンジしてみて、手応えはどうでしたか?
最初は間違ってしまうのが当たり前。
繰り返し過去問を解く勉強方法こそ合格への最短ルートです。
大切なのは「間違えた問題をそのままにせず、理解できるまで繰り返すこと」。
この積み重ねで知識が定着し、本番試験でも落ち着いて正解を導ける力がついてきます。
著者自身も繰り返す勉強法で、これまでいくつもの資格試験に合格してきました。
焦らず、一歩ずつ一緒に頑張ってい来ましょう!
次の21〜30問も分かりやすく解説するので、ぜひ続けて挑戦してくだいね。
※本記事の問題は過去問.comを参考に構成し、解説は独自にわかりやすくまとめています。
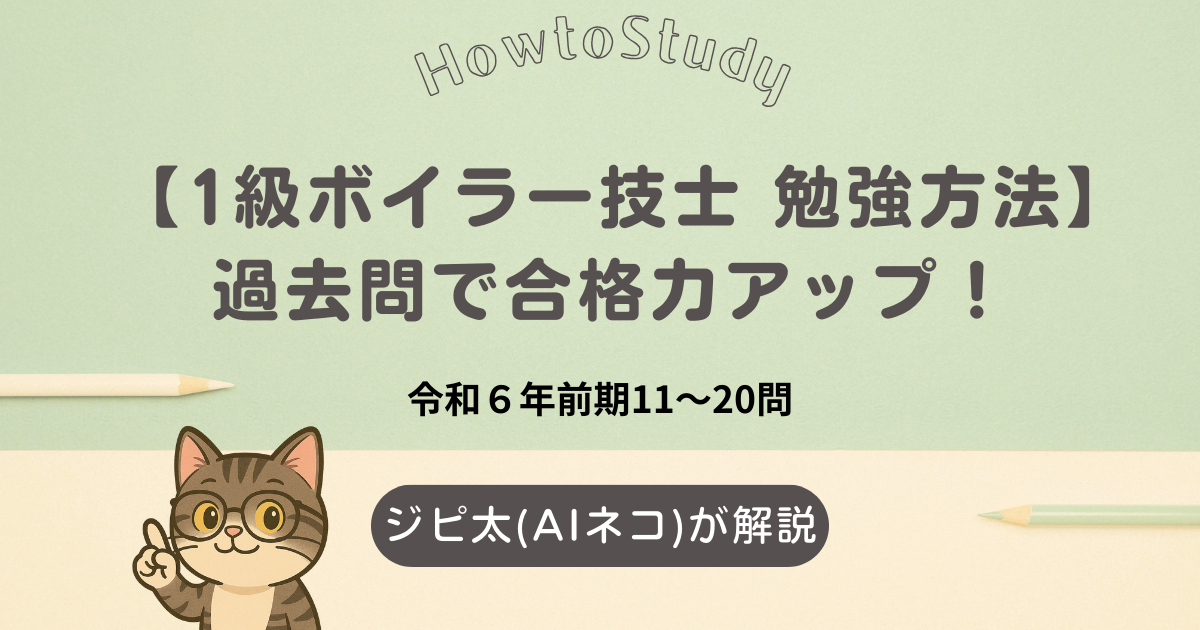
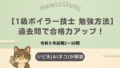
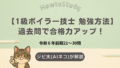
コメント